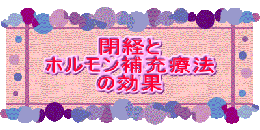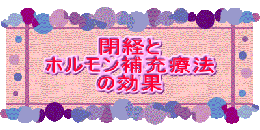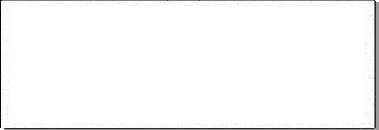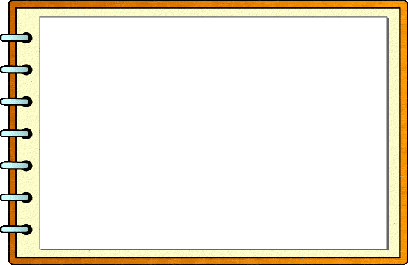「ホルモン補充療法」は、閉経後女性を「いつまでも若く美しくいきいきとさせ」、
生活の質を向上させるものとして認知されており、欧米では閉経後女性の30〜50%が受けています。その結果、更年期障害が軽快する他、骨折の件数が減少する、心臓病が減少するなど、多大の貢献しています。 一方日本では、この「ホルモン補充療法」を閉経後女性の2%弱しか受けていません。その原因として、患者が「ホルモン補充療法」を知らないか、もし知っていてもその効果や副作用について疑念を持っている可能性が指摘されています。しかし最近、婦人雑誌などでしばしば「ホルモン補充療法」の効用が載せられることから、本療法を希望される患者が増加しつつあることも事実です。
更年期障害の改善 活発に働いて女性ホルモンを分泌している卵巣は、50歳前後で急激にその機能を停止してしまい
ます。その結果、女性は40歳代後半になると、それまで順調に訪れていた月経が不規則になり、やがて閉経となりますが、
その過程で更年期を迎えます。 更年期には、女性ホルモンが急激に減少することと、その時期の心因的ストレスなどに
よって、心身に様々な症状が出現します。これらが「更年期障害」ですが、この「更年期障害」に対し「ホルモン補充療法」は
非常に有効です。
骨粗鬆症の予防・治療 女性ホルモンのうちエストロゲンは、骨の形成に重要なホルモンです。40歳を過ぎると女性
では骨量が徐々に低下してきますが、更年期になると、急激に「骨粗鬆症」となる場合があることが知られています。この
「骨粗鬆症」に対し、「ホルモン補充療法」は非常に有効であり、減少した骨量を増加させることも可能な場合が多いものです。
皮膚症状を改善し、皮膚を若々しく保つ 更年期になると、皮膚も薄くなり、皮膚の乾燥症状や掻痒感が出現
することがあります。これら皮膚症状にも、「ホルモン補充療法」が有効であり、皮膚を若々しく保つ作用があります。
性交障害など、生殖器症状の改善 更年期になると、生殖器の粘膜も萎縮し、外陰部の掻痒感や膣粘膜の乾燥
症状が出現することがあります。とくに膣粘膜の乾燥は、性交時の外陰部疼痛の原因となり、更年期以降のスムーズな性
生活を障害します。このような生殖器症状に対し、「ホルモン補充療法」は非常に有効です。
失禁など、泌尿器症状の改善 また更年期には、膀胱や尿道の粘膜が萎縮し、少し腹圧をかけただけで尿がもれ
たり、尿失禁を起こすことがあります。このような泌尿器症状に対しても、「ホルモン補充療法」は有効とされています。
脂質の改善・動脈硬化の予防 女性ホルモン(エストロゲン)は、LDL一コレステロール(悪玉)を減らし、
HDL−コレステロール(善玉)を増やす作用があります。そのため、更年期になると、急にLDL−コレステロール(悪玉)が
増加して「高脂血症」となることがあります。最近では、わが国の50歳代・60歳代の女性は半数以上が「高脂血症」の状態
です。この「高脂血症」は「動脈硬化」を引き起こし、心筋梗塞や狭心症などの「虚血性心疾患」や「脳梗塞」の原因となり
ます。閉経後の女性が「ホルモン補充療法」を受けると、「高脂血症」が著明に改善されます。その結果「虚血性心疾患」が
半減するとされています。欧米では女性の死因の第一位は「虚血性心疾患」であることから、アメリカ心臓学会では、「虚血
性心疾患」を有する閉経後女性は全員、またLDL−コレステロールの高い閉経後女性はできるだけ、「ホルモン補充療法」を
受けるべきと勧告しています。
アルツハイマー病の予防や記憶などの脳機能の改善 更年期を過ぎると物忘れが激しくなり、ときにかなり
早期に「痴呆」まで進行するアルツハイマー病を発症することがあります。「ホルモン補充療法」はこのアルツハイマー病の
発症を遅らせることが知られています。また、「ホルモン補充療法」は、閉経後女性の記憶や脳血流を改善することが報告
されており、エストロゲンの脳機能に及ぼす影響が臨床の分野でも次第に明らかにされつつあります。
「ホルモン補充療法」の有害事象としては、乳房の張りや乳房痛、頭痛、むくみ、腹部膨満感、吐き気などがあります。
また、子宮内膜が肥厚してきますので、破綻出血が起こる場合があります。しかし、これらの有害事象は、治療薬や投与
法を調節することによって改善されることが多いものです。また、以前、子宮体癌(子宮内膜癌)と乳癌を増加させる危険
性が指摘されていましたが、子宮体癌は現在の治療法(黄体ホルモン併用)ではむしろ減少すると考えられ ています。
また、乳癌については、女性ホルモン感受性乳癌の増殖促進が懸念されているものの、その増加率はそれほど高くはなく
(増加しないという報告から最高で1・5倍になるという報告まであるが確定していない)、もし発症しても定期検診を行うこと
により早期発見・治療が可能と考えられています。そのため、「ホルモン補充療法」を行う際は、1年から半年に一度、子宮
癌検診と乳癌検診を施行することが奨励されています。さらに、「ホルモン補充療法」により 肺癌や大腸癌はむしろ減少
すると報告されています。 最近注目されているものに静脈血栓症があり、これは確実に増加するようです。 ただし、その
頻度はそもそも少なく、わが国では欧米と比較してさらに希な有害事象ですが、易血栓性のある症例には「ホルモン補充
療法」は投与すべきでないとされています。
長寿科学総合研究事業(厚生省研究費補助)
高齢女性の健康増進のためのホルモン補充療法に関する総合研究班
東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座・教授 大内尉義(班長)
東京大学大学院医学系研究科生殖内分泌学講座・教授 武谷雄二
獨協 医科大学越谷病院産婦人科・教授 大蔵健義
北海道大学医学部附属病院循環器内科・助手 佐久間一郎
国際医療福祉大学医療福祉学部医療経営管理学科・教授 佐頗員一郎
東京都老人医療センタ←内分泌科・医長 細井孝之
−ホルモン補充療法の注意事項−